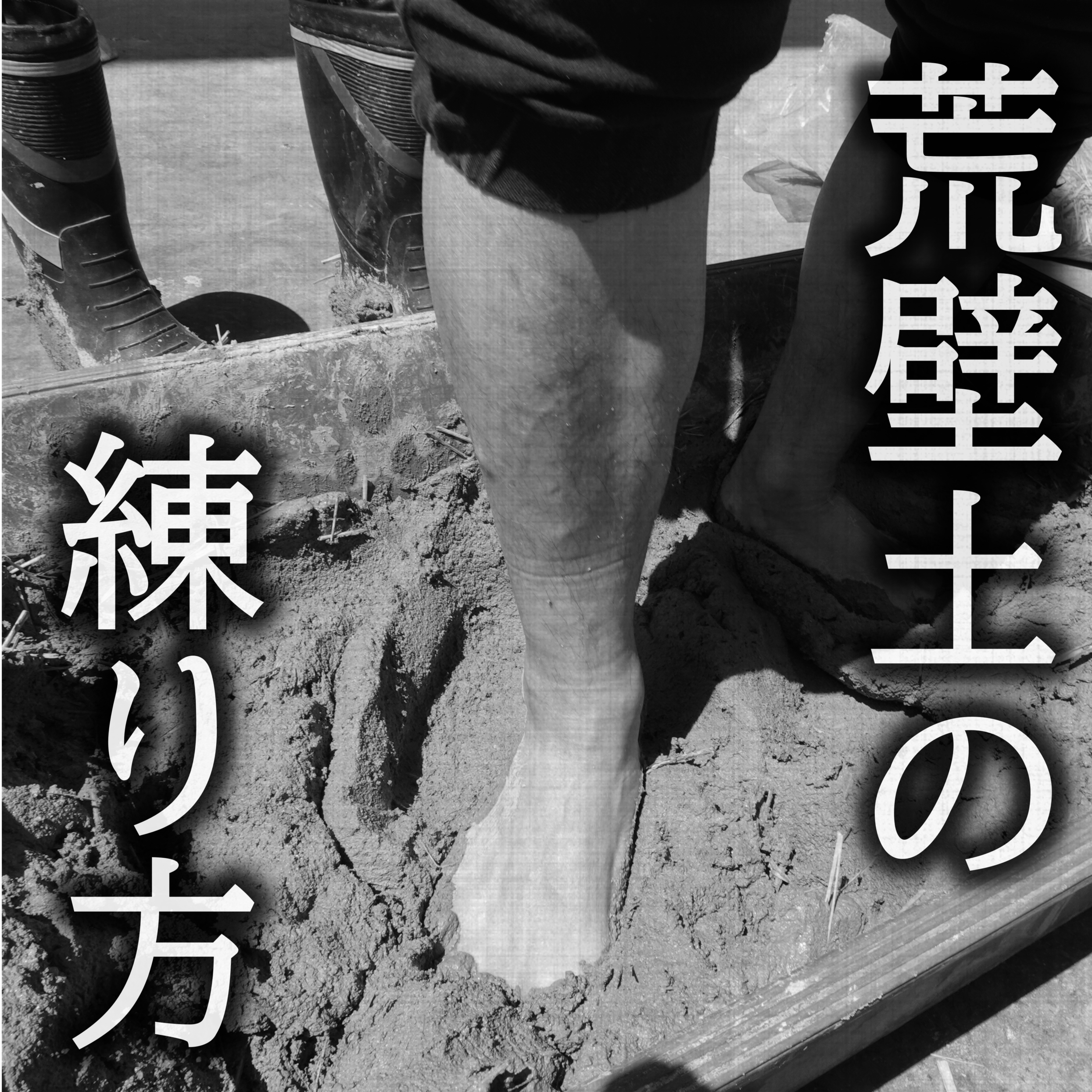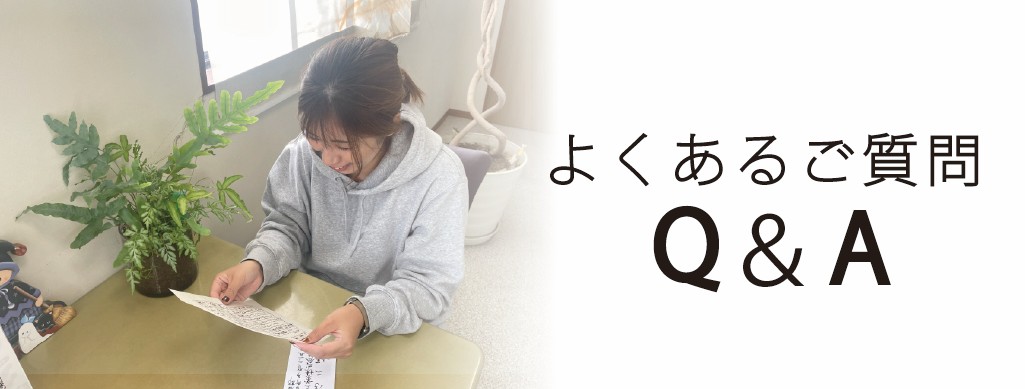文化財の改修工事などに漆喰をお考えのお客様、当社にはノウハウがあります
文化財に使う伝統的な漆喰についてはご相談下さい
国宝になった松江城天守の近くにあり、1969年に県有形文化財にしてされた興雲閣の保存修理工事が完了したので行ってきました。

興雲閣は洋風建築に和の意匠を取り入れた擬洋風建築で、1903年に松江城公園内に建てられ4年後には当時皇太子だった大正天皇が山陰道行啓した時の宿泊施設として使われた歴史ある建物です。
老朽化が進んでいたため、耐震補強と復元工事を2013年11月より開始し、この度完了しました。
国宝松江城のすぐ隣ですので皆様も足を運ぶ機会がございましたらぜひお立ち寄りください。




文化財に使用する漆喰材料、施工方法はご相談ください!